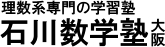作者別: 石川数学塾大阪
職-冬講日記(30)
男は仕事を捨てたいと思っていました。重圧に押しつぶされそうになっていたからです。
うまい具合にタイミングをつかんで、男は仕事を捨てました。
全て放り出して、まるっきり違う、全く新しい仕事をしたいと思い、そうしました。
しかし、奇妙なことに気がつきました。
いつのまにか、あの圧殺されそうな仕事に、戻っていこう、戻っていこうとする己がいました。
仕事捨てて三年後、男は仕事に戻ろうとしました。
ところが仕事のほうは、男の身勝手を許してくれませんでした。
男は大変な苦労をして、業界に復帰し、今に至っております。
ごくたまに、男は「引退したい」と思う年になりました。
しかしながら、仕事をできることの喜びが、男を思いとどまらせています。
男はいつまで仕事を続けるつもりなのでしょうか。
もはやおそらく、わからなくなっているのかもしれません。
それでも男は、魂の叫びとでもいうべきものに、今日も突き動かされて、出勤します。
この業界を見渡すと、そこらじゅうにたくさん、掃いて捨てるほどにいる、一人の男として。
Z-冬講日記(29)
今年も、フェアレディZ、好調であります。
ちょっとアクセルを踏みますと、グウォーンと加速します。爽快です。
もちろん交通法規を遵守しております。Zとともに、無事故・無違反です。
小生大満足なのですが、周辺はけっこうイラついております。
曰く「荷物が積めない」。はい、ゴルフバッグがドカンと入る程度です。
曰く「運転しずらい」。はい、コンパクトカーやファミリーカーではありませんから。
曰く「タイヤ一本からして、コストがかかり過ぎ」。はい、宿命でございます。生きてる限り、ゼニはかかりますので。
笑ってやり過ごしているうちは良いのですが、真面目に論難されると、本当に厄介です。
そんな時は、「まあまあ」なんぞとなだめすかして、助手席に乗せてあげ、グウォーンとエグゾースト響かせ、心地よく疾走しますと、およそ誰もが全てを忘れてくれます。
幼いころから大好きだった車ですから、大切にしたいと思います。
郷-冬講日記(28)
久しぶりですね。坂上郎女嬢に、唸っていただきましょう。『万葉集』からです
故郷(ふるさと)の 飛鳥はあれど あをによし 奈良の明日香を 見らくしゆしも
奈良ホテルから、道を挟んでほぼ真向いあたり、タイ料理をいただいて、背後の奥山に遊んでおりますと、ここらあたりは平城京の飛鳥だ…と書かれております。何のこっちゃ?と、不思議に思っておりましたが、最近納得いたしました。
明日香の飛鳥寺から、建材を運んできて、元興寺を組み立てた。だから人々は、元興寺界隈に、飛鳥寺と明日香の面影を見たのだと。
郎女嬢も、きっと同じ感覚でいらっしゃったのでしょう。
人は引っ越ししても、引っ越し先に郷を探すものだと。
小生も正月休みを利用して、西三河の郷に少しだけ帰っておりましたが、小生不思議なことに、三河に大和を見ることがありません。大和どころか、磯城(しき)も、磐余(いわれ)も、飛鳥も、添(そふ)も、葛城も、忍海(おしみ)も、普段歩いておりますアチャコチャを、郷に見ることがないのです。
なんでだろう?と、しばし小考、人生の三分の二を関西で過ごしましたから、こちらが小生の郷になってしまったからだろうと、ひとり大きくうなずいてしまいました。
神-冬講日記(27)
新春早々、神様談義を楽しんでまいりました。
「天孫降臨は、垂直神話の典型でして、大陸系の神様のありようなんです。たとえば新羅の始祖王の生誕説話に、大きな鳥が飛んできて、卵を産み落としていった。そこから皇統が始まった、なんてものがあります」。
「それにも拘らず、日本神話の神様には、南洋系の水平神話もたくさん取り入れられています。オオナムチ(オオクニヌシのことです)と共に葦原中つ国を造ったスクナビコナ(一寸法師のモデルです)は、海の彼方からやってきたとか」。
「倭国の神様と言えば、イザナギ・イザナミから三貴子(アマテラス・ツクヨミ・スザノオ)が、メインストリームと思われがちですが、違うんじゃないかと思うのです。『古事記』(上巻)冒頭に曰く、アメノミナカヌシ(ド真ん中)・カンムスビ(天上神の創造神)・タカミムスビ(地上神の創造神)…ではないのかと」。
「伊勢神宮が本来祀っていました神は、タカミムスビだろうと考えられます。式年遷宮の時に、床下を剥がしますと、木が一本立て差してある…これこそが、タカギノカミ、すなわちタカミムスビであろうと」。
議論は果てることなく延々と続きまして、たいへん楽しいひとときを過ごせました。
冬講日記、ご覧ください!
こんにちは。学園前教室の杉浦です。
冬講日記、書いています。
この二週間は、じっくり落ち着いて書いておりました。
受験直前のこの時期こそ、落ち着いて毎日を過ごしたいものですね。
以下のリンクからたどってみてください。
http://blog.livedoor.jp/ishikawasugakujuku/archives/cat_910297.html
二週間分の記事です。
時-冬講日記(16)
逢-冬講日記(17)
爽-冬講日記(18)
邪-冬講日記(19)
民-冬講日記(20)
営-冬講日記(21)
惑-冬講日記(22)
病-冬講日記(23)
雨-冬講日記(24)
暦-冬講日記(25)
新-冬講日記(26)
新-冬講日記(26)
もういくつ寝ると、新年でしょうか。新しい年が、すぐそこまで迫っております。
昨年も、一昨年も、この時期にこのようなことを書いていた記憶があります。あまり変わりがありません。
変わったことといいますと、「新」の字を見ると、特別な思いが湧きおこってくるようになったことでしょうか。
古代中国に「新」なる王朝があったことは、意外と知られておりません。小生も倭国の古代史を勉強して、ついでに思い出すまで、きれいさっぱり忘れておりました(笑)。
「夏・殷・周・春秋・戦国・秦・前漢・後漢・魏呉蜀・五胡十六国…」と、順ぐりにお経を唱えますと、前漢と後漢の間に、ほんの少し存在した王朝です。
王莽という王様が、いちおう前漢から禅譲されて始めたのですが、国内改革が拙速で、諸蕃に失礼なあまり反撃を誘い、赤眉・緑林の乱によって滅亡した、一代限りの王朝でした。
なになに、先生、中国の古代史まで始めはったのですか?と、いぶかられてしまいそうですが、さにあらず、この王朝がいびつな国内改革の一環として鋳造した「貨泉」という硬貨に興味があるのです。
青銅貨ですから、錆びついて出土することが多いのですが、これ、わが国の弥生遺跡から、けっこう出土するそうです。
この貨幣を鋳造していた「新」が、ほんとに短い期間しか存在しませんでしたので、流通、伝世など、あまり細かく勘案しなくても、遺跡や古墳の時代特定ができる、そんな便利な遺物なんですね。
新年の「新」の字を見ると、こんなことばかり頭をよぎるようになってきました。
新しい年が、すばらしい年でありますように。
暦-冬講日記(25)
新入生歓迎カレンダーを、今年も送っていただきました。京都大学ボート部の皆さん、今年もありがとうございます!
お礼のお手紙を出させていただきました。差し障りない範囲で、公開させていただきます。
***お手紙ここから***
京都大学ボート部 御中
今年もボート部カレンダー、ありがとうございました。私も生徒も大喜びです。
合宿所から宅急便にかけていただき、申し訳ありません。将来一人でも多く京都大学に入学して、ボート部に入部するよう、奮闘いたします。
私も妻(明日香)も元気であります。妻は勤務先が、多少遠くの学校に変わったようで、通勤時間が若干増えたそうです。
今年度も、お盆の明日香村合宿、春・初夏・秋の歩こう会、京大11月祭見学ツアーなど、体力メインのイベントを乗り切りまして、来年度も、もう一年、なんとか仕事を続けることができそうな気がしてきました。
最近、古くからの卒業生を、明日香村奥明日香・柏森の「さらら」さんにお誘いして、旧交を温めております。奈良近辺に来られる機会がありましたら、是非ともご連絡ください。
「さらら御膳」など食べながら、近況をお聞かせいただくと幸いです。
ライブドアブログ「石川数学塾大阪」に冬講日記を連載中です。よろしければ、お読みいただきますと幸いです。
お風邪など召されませんよう。ご多幸を祈念いたしております。
石川数学塾大阪・学園前教室
杉浦 功
***お手紙ここまで(表記を一部修正してあります)***
末永くおつきあいさせていただきたいと思っております。
雨-冬講日記(24)
晴れの日も多いですが、雨も多い今年の冬です。
幼いころ、無邪気に雨を喜んでおりました。
♪あめあめ ふれふれ かあさんが じゃのめで おむかい うれしいな♪
傘と長靴があれば、雨には濡れないものだと信じておりました(笑)。
けっこう老成坊主であった小生は、そうこうするうちに口ずさみ始めました。
♪夜明けの停車場に ふる雨はつめたい♪
昔懐かしい、石橋正次さんであります。
十代後半には、もはやド演歌でありました(笑)。
♪雨にぬれながら たたずむ人がいる 傘の花が咲く 土曜の昼下がり♪
直立不動の三善英史さんであります。
以後、今日に至るまで、この路線は不動でありました。
♪雨々ふれふれ もっとふれ 私のいい人 つれて来い♪
鼻歌は、もっぱら八代亜紀さんであります。
世に棲む日々も、歌につれつつ…。
12/28(水)~1/3(火)はお休みになります。
石川数学塾大阪では、12/28(水)~11/3(火)は塾カレンダーにより、通常授業が休みになります。くれぐれもお間違いのないようにしてください。
なお、12/28(水)、29(木)、30(金)は午前・午後の冬期講習は開講していますので、どしどしご参加ください。