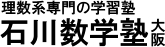男は怒っておりました。半世紀に渡って、怒り続けておりました。
「砦」が陥落して、はや半世紀。砦が無くとも、持ちこたえたことを誇りに思う反面、日々確実に狭まってくる包囲網に、焦燥を隠しきれなかったのでしょう。
一億挙げてファシズムの時代、男が理想とした寄るべは、小さな小さな経済誌でした。『東洋経済新報』といいました。
国際紛争を軍事力で解決することが「あたりまえ」だったあの時代、のちに戦後我が国の首班を務める主筆が「貿易立国」を提唱しました。
「拙速はイカン。知恵を絞らねばイカン。平和は尊い。どれほど豊かな未来を約束しようが、平和に対する挑戦を許さん!」
主筆の口癖が、いつのまにか、男に乗り移っていました。
男にとって現世を呪うことは、「やむにやまれぬ」至誠に根ざすものだったにちがいありません。
男はまだまだ生腐っております。
一敗地にまみれ、しばらく冷蔵庫で頭を冷やし、もう幾たびかの復活を果たすまで、雌伏することでしょう。